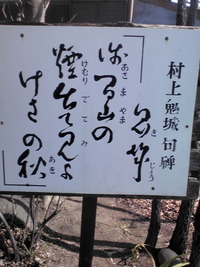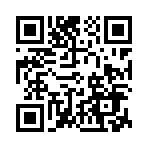気になる場所(ポイント)があります。1月15日の金田水車で紹介した場所です。右の写真がその時に載せられなかった馬頭観世音です。金田水車と読めましたでしょうか。
さて左の写真はそこから、南西を撮ったものです。上並榎城の土塁跡と紹介した場所です。
ここが高崎市史( 昭和44年版第一巻)に、古墳として紹介されていました。
昭和37年に芋穴を掘っていて石室を発見したそうです。水害のため形が古墳らしくなく登録もれとなっていたものとあります。確かに昭和十年の古墳総覧にはありません。載ったとすれば、六郷地区第24号稲荷塚、円墳、上並榎字南857と載ったことでしょう。
出土品として、直刀三振、刀鍔一個、曲玉六個、金環二個、矢尻五、石宝六、糸紡ぎ石、人骨、歯、管玉一個が出ました。
古墳の成立は、七世紀中頃のものと推定しています。
この場所のことを整理してみましょう。 御紹介したように、まず円形の古墳でした。そして戦国時代には並榎庄九郎なるものの、城の二の丸の東端の土塁となりました。その後農家の屋敷稲荷と竹薮となりました。
そして、目の前を、水車が回り、やがて汽車が走るようになりました。
祖父と散歩した五十年前には、古墳は未盗掘だったのです、そうですその時にはまだ石棺の中に人骨があった訳です。
もしかして、その死者のDNAを持つた二人を見守る古墳だつたのかも知れません。
それにしても、あの時祖父は何を言いかけたのだろうか、水車のあった、汽車の線路脇の、石棺に入ったままの死者の見下ろすこの谷のほとりに立って、何かを言おうとして口ごもった祖父。
私にとって気になるこのポイントは謎めいたままの表情で、五十年いや、一千年前と同じままに、今私の前にあります。
否、私の中に流れるなにかが、長いあいだこの景色を見続けていたのかもしれません。