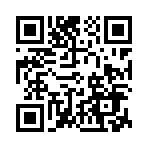ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 



 飯塚町字鼠屋敷(ねずみやしき)と言う所です。
飯塚町字鼠屋敷(ねずみやしき)と言う所です。  写真は飯塚の東の薬師です。約二百米、西にある薬師様と向かい合っています。誰云うか飯塚の夫婦薬師と云われています。ともに、箕輪城主長野業政公によって大永三年(1525年)に祀られたとあります。飯塚城(別称北城)も常福寺もこの夫婦薬師にも長野氏の影がちらつきます。
写真は飯塚の東の薬師です。約二百米、西にある薬師様と向かい合っています。誰云うか飯塚の夫婦薬師と云われています。ともに、箕輪城主長野業政公によって大永三年(1525年)に祀られたとあります。飯塚城(別称北城)も常福寺もこの夫婦薬師にも長野氏の影がちらつきます。 シリーズ其の四で飯塚城跡に潜入した時に奇妙なものを、発見してしまいました。写真の首座像です。城の西半分占める常福寺に背を向けて東の空地と梅林を見続ける石仏と塔でした。
シリーズ其の四で飯塚城跡に潜入した時に奇妙なものを、発見してしまいました。写真の首座像です。城の西半分占める常福寺に背を向けて東の空地と梅林を見続ける石仏と塔でした。| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |