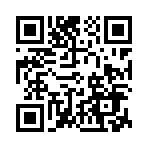”昭和三年十月十九日の日記より抜粋"
十月十九日(金)晴。上州高崎光明寺に妻と共に先祖の墓に参る。墓参を終へて後に烏川の畔に至り、遥かに榛名碓氷の連峰を眺めながら我が少年時代のこと共を思い出した。
柳川町に我が父の家の跡をたずねた。初めて手習いに行きし白井老先生の邸宅の前を過ぎた。熊野神社は我が迷信時代の崇拝物である。この日丁度その祭礼であった。凡てが六十年前のことである。山の形はかわらず、川は依然として流れる。
そのなかに我が少年時代の友なる淡水魚類は棲む。ただ漁に耽る我を誡める父の声を聞かない。
昭和五年三月二十八日朝死亡。
妻は三度目の妻である”シズ”。
札幌農学校では水産学を専攻し
北海道開拓使勧業課漁猟科に勤務。
光明寺は若松町にて真言宗。
熊野神社は高崎神社のこと、
10月19日は秋の例大祭。
”明治六年の旧高崎藩貫属明細短冊帳上巻”です
鑑三の父は内村宣之、祖父は内村善八、
高祖父は内村丑之助その父は内村杢兵衛。
第五区小一区百三十六番屋敷とは上記の柳川町の父の家。
文久元年三月二十三日に江戸小石川鳶坂の藩武家長屋生まれ。
父の謹慎に伴い柳川町に移り住んだのは慶応二年十二月、鑑三五歳の時。
明治六年には、東京外国語学校入学のため東京へ出ています。
その間に父の石巻県への赴任等もあり、高崎に居たのは
70歳の人生のうち約5年間だけのようです。


 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。