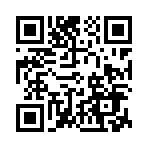写真は飯塚の東の薬師です。約二百米、西にある薬師様と向かい合っています。誰云うか飯塚の夫婦薬師と云われています。ともに、箕輪城主長野業政公によって大永三年(1525年)に祀られたとあります。飯塚城(別称北城)も常福寺もこの夫婦薬師にも長野氏の影がちらつきます。
写真は飯塚の東の薬師です。約二百米、西にある薬師様と向かい合っています。誰云うか飯塚の夫婦薬師と云われています。ともに、箕輪城主長野業政公によって大永三年(1525年)に祀られたとあります。飯塚城(別称北城)も常福寺もこの夫婦薬師にも長野氏の影がちらつきます。さて、東の薬師です、享保年間に小平与惣治という人が眼病の平癒のお礼に堂を再興したと由来の表示にあります。
ここで、誤謬の小発見です。表示板には享保年間 (1755)とあります、享保年間なら1716から1735年であり1755年なら宝暦五年ではないでしょうか。
東の薬師様に向かって左手前に、奉納薬師如来と書かれた石塔がありました、年号は判読できませんが、三月大吉日当村、小平左平治倅、小平佐右衛門と読めました。小平与惣治さんの御子孫なのでしょうか。
さらに時代は下って昭和の始めの頃、内山信次氏によると畑にするために小さな塚を崩していると、薬師仏を見つけ昭和八年に堂を建てたとあります。また近くに庵があったとの言い伝えもあったとのことです。内山氏は飯塚に小庵の名前を三つあげそのうちの一つを想定しています。
ところがです、前回紹介した常黙庵がその中の一つだったのです。つまり、三つから二つに絞り込めたのです。これは偉大なる小発見でした。
最後に内山氏等の一所一勝運動による指定の結果、今の薬師堂が再建されたそうです。
話が飯塚城から遠ざかってしまいました。が、この城には城主がみあたりません、下之城同様による和田氏直轄地だったであろう、とのことです。いずれにしても外堀をぐるぐる巡るだけで本丸に入れません。もっとも入ってもどうせ空き地なのですが。まだ続きますゾクゾクするような話をしたいと思います。飯塚常仙かな。