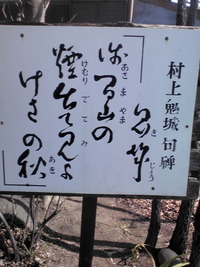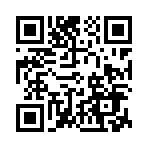明けましておめでとうございます。今年もよろしく。正月三日は元三大師の縁日です。そう新比叡山天龍護国寺です、今年はここから始めましょう。
平安初期の貞観六年慈覚大師の創建、僧坊三百余を配した東国随一の名刹。高崎に現存する最古寺です。
創建後、護国鎮護のため稲荷、愛宕、北野、不動の四社を周辺に配したという。まず稲荷、寺宝並榎八景絵図の稲荷山の暮雪の稲荷である。和歌は佳明(本名大沢勝弥 五十石取り馬廻り役の高崎藩士)。漢詩は本名梶山与惣右衛門の作、余談だが大沢姓は今も上並榎に多く旧家、梶山家は本町の問屋名主、佐渡御金蔵、高札場のあった場所が居宅。
和歌には神に捧げる白木綿のように降り積もった雪が稲荷の燈明でひときわ美しい稲荷山がうたわれている。
稲荷山とは上並榎五反田186.187にあった当地最大の前方後円墳である。
明治25年の社殿改築の際、発見された石棺は現在護国寺境内にある。正確には舟型石棺の蓋である。昭和36年頃までは稲荷の社のある後円部が残っていた。私も微かにぼうぼうとした冬景色の中に一度だけ古墳を見たような気がする。
いずれにしても今は何も無い。人々の記憶以外は何一つ存在しない。
せめてもとその痕跡をもとめて、行く捨蚕であった。新室田街道が長野堰を渡る橋その橋の名は稲荷橋、真木病院の南に稲荷ハイツと稲荷コート、もひとつおまけに稲荷荘。そうそう稲荷山の土は四中の校庭整備に使われたとか。
せめて標識だけでもとおもうのですが・そうおもいませんか!迷道院さん!
多少興奮気味の捨蚕であった。
今日はここまで、つぎは愛宕です。
平安初期の貞観六年慈覚大師の創建、僧坊三百余を配した東国随一の名刹。高崎に現存する最古寺です。
創建後、護国鎮護のため稲荷、愛宕、北野、不動の四社を周辺に配したという。まず稲荷、寺宝並榎八景絵図の稲荷山の暮雪の稲荷である。和歌は佳明(本名大沢勝弥 五十石取り馬廻り役の高崎藩士)。漢詩は本名梶山与惣右衛門の作、余談だが大沢姓は今も上並榎に多く旧家、梶山家は本町の問屋名主、佐渡御金蔵、高札場のあった場所が居宅。
和歌には神に捧げる白木綿のように降り積もった雪が稲荷の燈明でひときわ美しい稲荷山がうたわれている。
稲荷山とは上並榎五反田186.187にあった当地最大の前方後円墳である。
明治25年の社殿改築の際、発見された石棺は現在護国寺境内にある。正確には舟型石棺の蓋である。昭和36年頃までは稲荷の社のある後円部が残っていた。私も微かにぼうぼうとした冬景色の中に一度だけ古墳を見たような気がする。
いずれにしても今は何も無い。人々の記憶以外は何一つ存在しない。
せめてもとその痕跡をもとめて、行く捨蚕であった。新室田街道が長野堰を渡る橋その橋の名は稲荷橋、真木病院の南に稲荷ハイツと稲荷コート、もひとつおまけに稲荷荘。そうそう稲荷山の土は四中の校庭整備に使われたとか。
せめて標識だけでもとおもうのですが・そうおもいませんか!迷道院さん!
多少興奮気味の捨蚕であった。
今日はここまで、つぎは愛宕です。