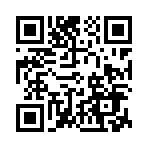k
高崎には有名な八幡様が、二つあります。
板鼻八幡宮(天徳元年・957年)と、
山名八幡宮(文治年間・1185~1190年)です。
前者は旧碓井郡八幡村で、”八幡の八幡さま”
後者は旧多野郡八幡村で、”山名の八幡さま”
今回は前者、
”上野国一社八幡宮”の
”八幡の八幡さま”です。
(地主神社のこと)
八幡さまの西北隅にいまも地主稲荷神社があります。
創建伝説の”青目竹”によると、かってここは稲荷社の森でした。
ある時、衣冠正しき老翁が、対岸の鼻高から、香煎(麦こがし)をご馳走になりながら、稲荷の森にむけて竹の杖を投げたそうです。杖は翼のある矢のごとく飛んで、逆さに根付き、この地に八幡様が鎮座したそうです。
いまでも毎年、八幡宮に香煎が献じられますが、まず地主稲荷神社に献納されるそうです。
(別当寺のこと)
八幡様のすぐ東に真言宗の大聖護国寺があります。
建保二年(1214年)の開山から少なくとも寛永期(1624~44年)まで別当寺でした。
突然ですが、東京の小石川音羽の護国寺をご存知ですか。
一度、お茶会の道具持ちで仙台平の袴で行きましたが、すごいお寺でした。
三条実美、大隈重信、山縣有朋、團琢磨親子、野間清治等々の墓所が
ありました。
天明元年(1681年)に創建されたこの音羽の護国寺の初代管主亮賢(りょうけん)は、ここ八幡の大聖護国寺の第24代住職でした。徳川綱吉から生母桂昌院の祈願寺の開山を命じられたそうです。寺領三百石でした。
別当寺はその後、天台宗神徳寺に、幕末の焼失後はその本寺の板鼻の称名寺が別当を勤めたそうです。 (それで、地主神社の手前に日枝神社がある理由が、理解できました)
(高崎駅より6K983M)

高崎には有名な八幡様が、二つあります。
板鼻八幡宮(天徳元年・957年)と、
山名八幡宮(文治年間・1185~1190年)です。
前者は旧碓井郡八幡村で、”八幡の八幡さま”
後者は旧多野郡八幡村で、”山名の八幡さま”
今回は前者、
”上野国一社八幡宮”の
”八幡の八幡さま”です。
(地主神社のこと)
八幡さまの西北隅にいまも地主稲荷神社があります。
創建伝説の”青目竹”によると、かってここは稲荷社の森でした。
ある時、衣冠正しき老翁が、対岸の鼻高から、香煎(麦こがし)をご馳走になりながら、稲荷の森にむけて竹の杖を投げたそうです。杖は翼のある矢のごとく飛んで、逆さに根付き、この地に八幡様が鎮座したそうです。
いまでも毎年、八幡宮に香煎が献じられますが、まず地主稲荷神社に献納されるそうです。
(別当寺のこと)
八幡様のすぐ東に真言宗の大聖護国寺があります。
建保二年(1214年)の開山から少なくとも寛永期(1624~44年)まで別当寺でした。
突然ですが、東京の小石川音羽の護国寺をご存知ですか。
一度、お茶会の道具持ちで仙台平の袴で行きましたが、すごいお寺でした。
三条実美、大隈重信、山縣有朋、團琢磨親子、野間清治等々の墓所が
ありました。
天明元年(1681年)に創建されたこの音羽の護国寺の初代管主亮賢(りょうけん)は、ここ八幡の大聖護国寺の第24代住職でした。徳川綱吉から生母桂昌院の祈願寺の開山を命じられたそうです。寺領三百石でした。
別当寺はその後、天台宗神徳寺に、幕末の焼失後はその本寺の板鼻の称名寺が別当を勤めたそうです。 (それで、地主神社の手前に日枝神社がある理由が、理解できました)
(高崎駅より6K983M)




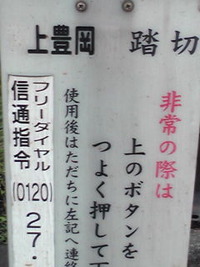

 at 2010年05月19日 15:39
at 2010年05月19日 15:39