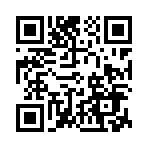井伊掃部頭直弼、の直筆の書状です。
桜田門外の変で有名な方ですね。
まず、タヌキの絵のような花押が目に入ります。
その上に直弼の直筆のサインがあります、その上に、二月二十一日とあります。時は、嘉永六年(1853年)のことです。
その右に、井掃部頭とあります。中国風に洒落て、伊を削って一字で井です。
掃部頭(かもんのかみ)とは、掃部寮の長官のこと、この寮は宮中の清掃や式場の設営を担当する部署でした。
でも、実際に宮中で掃除指揮した訳ではありません。従五位の官位です。
この年、嘉永六年六月三日にペリーの黒船が浦賀にやってきました。
黒船来航から明治維新までを幕末と呼ぶそうです。
(まさに嵐のような幕末は15年間だけだつたんですね。)
直弼は嘉永三年(1850年)彦根藩第15代藩主になります。この時掃部頭となります。
安政の大地震は、安政二年十月二日の夜の10時頃、M6・9です.
大老になるのは、安政五年(1857年)四月です。
126名の受刑者をだした、あの安政の大獄は安政五年~六年のことです。
桜田門外の変は、安政七年(1860年)三月三日です。
直弼にとって、まさに嵐の前の静けさ、のような嘉永六年の春だったのでしょう。
最初の字は為ですが、その次は青陽(せいよう)、初春のことです。
(春は青、だから青春。秋は白、だから白秋。)
あて先は、安中市下後閑の、北野寺です、左最後の三文字です。 正確には威徳山吉祥院北野寺です。
北野寺とは、初代井伊直正からのお付き合いです。
なにせ、井伊直正の次二男の弁之助(井伊直孝、二代彦根城主)は、このお寺の薬師堂で育ったようなものです。
この薬師堂は寛政六年(1794年)に直弼の実父である、十一代藩主井伊直中により再建されています。
この手紙は直弼から北野寺への、お礼状です。何を頂戴したかというと、三行目の四文字です。
札守・巻数(さつしゅ・かんず)です。つまりお守りと、読経した度数を書いた短冊のことです。
最後は、恐恐不備で結んでいます。
たかが、157年前の手紙ですが。殆んど読めませんし、意味も解りませんでした。
我々が学んだ、勉強とは、一体全体なんだったのでしょうか。
最後に桜田門外の変は西暦で、1860.3.24日です。150年前の一昨日は、大雪だったんですね。
またまた余談ですが、井伊大老の首は、その後行方不明だそうです。田島武夫さんの本に、羽鳥類三が合羽に包み水戸藩邸に持ち込み、そこから高崎の宿大類まで持ってきたかもしれない、という話を読んだ記憶があるのですが。