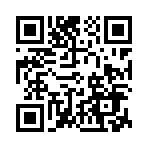当たり前のことですが、上信とは、電気鉄道だったんですね。
大正十年八月二十五日の臨時株主総会で、上野鉄道株式会社は上信電気鉄道株式会社に、社名変更しました。
社長は山田昌吉氏です。(明治9年1月16日誕生〜昭和19年五月十八日午後11時15分永眠)
まず上信です。上信とは上野と信濃、上州と信州、 いずれにしても、下仁田から峠を越えて小海線と接続する予定でした。
当時、佐久鉄道と呼ばれた小海線は、小諸から小海までの開通でした。(小諸〜小淵沢間78・9kmのうちの48・3km)
下仁田から南牧方面へ磐戸、余地峠をへて小海の五つ小諸よりの駅、羽黒下駅までの計画でした。
さて、電気のほうです。電化工事は大正12年〜13年にかけて主に工事が行われました。その結果、全長33・7kmを2時間15分かかった走行時間は1時間12分と約半分に短縮されました。
大正13年の電化開業当時、駅は13駅ありました。
ここに上信電鉄沿線名所案内絵図があります。
絵図にそってゼロ番線を出発しましょう。
始発駅の高崎には頼政公園、歩兵十五連隊、清水寺、小林山があります。烏川を渡ると山名です。 山名八幡、金井沢の碑、
山の上の碑、があります。10月15日の山名八幡宮の秋の祭礼には、山名駅の乗降客数は1万人を越えたそうです。
次は馬庭停留場、無人のため駅とは呼ばなかったそうです。鏑川の鉄橋を渡ると右に多胡碑をみつつ吉井です。次は新屋停留場、鏑川鮎簗、変電所、とあり次は福島、笹の森稲荷がみえます。ここでまた鏑川を渡り、富岡です。
原製糸所とあります、次の七日市停留場には蛇宮神社、一ノ宮には、貫前神社、北向観音、宇田観音。
神農原停留場には宮崎梅林、南蛇井すぎて、千平。不通(とうらず)橋に箱淵峡、トンネル潜って、下仁田駅に到着です。
13の駅がありましたか、正確には8つの駅と5つの無人の停留場ですが。
終着駅の下仁田駅には、赤く錆びた鉄路が捲くれ上がった状態で終わりになつています。
山田社長の夢の中断のように、青春の夢の残骸のように宙に捲くれて、終止符を打つていました。
話は少々ずれますが、
先日高崎市議会で、ある議員が例えば上信電鉄を市役所まで敷いて来て、市役所駅を創る話をしてました。
地下鉄にして国立病院前とでも名付けるたら、お年寄りも便利ですね、面白い発想ですね。
鶴見町の上信本社前を通ったら、是非とも、気と鉄の旧漢字に注意して見ていただければ幸いです。
話が長くなりました、とりあえず今日はここまで、終点です。
上信電鉄百年誌を参考にさせていただきました。