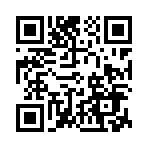(今朝の上毛新聞の県央版に、この記事が載りました)
新聞の写真で香を聴いている女の子(七歳)は、六人の正解者のひとりでした。
高崎藩主大河内氏のご先祖の源頼政にちなんだ、”新菖蒲(あやめ)香”です。
御家流の家元は、大河内氏の前の高崎藩主の安藤三代の御子孫です。
両家とも譜代大名ですが、大河内氏は新参譜代、安藤氏は三河譜代と区別されるそうです。
そう講話される堤克政氏は、大河内高崎藩の家老の御子孫にて、頼政神社の総代をなさっております。
鵺(ぬえ)退治で有名な源三位(げんざんみ)頼政卿(きょう)は、
鬼(酒呑童子)退治で有名な源頼光の曾孫さんです。
”五月雨に池のまこもの水まして
いずれあやめと引きぞわずらふ”
この一首で頼政は菖蒲御前の心を射止めたとか。
源氏香、七夕香、三夕香、除夜香、と様々な香立てがありますが、その背景には膨大な古典の知識の山脈がありました。
お香は、たんに臭覚の問題だけでは、どうも収まらないようです。